目次
くも膜下出血についてのオススメ記事
リスク管理のコツ
リスク管理を行うためには、対象者の患っている疾患から病態を把握し、カルテ情報やフィジカルアセスメント等を行うことが必要になります。
フィジカルアセスメントにおいては、その数値だけでなく、なぜその数値になるのか、またその意味を知ることで、対象者の状態像の理解に役立ちます。
今回は、くも膜下出血の病態理解として、予後に影響を与える一時的損傷(直接的脳損傷)についてまとめて行きたいと思います。
くも膜下出血の概要と脳の解剖学的知識
くも膜下出血とは
くも膜下腔へ出血をきたした疾患がくも膜下出血である。
外傷等を除いた内因性疾患ではその原因の85 %は脳動脈瘤破裂によるもので、10%が原因不明、5 %が脳動静脈奇形など他の疾患によるとされる。
破裂脳動脈瘤では、急性期の再破裂防止の問題とともに、脳血管攣縮による脳虚血や正常圧水頭症などのさまざまな問題が、発症後およそ1ヶ月の間に続発し、治療法が進歩した現代においても、死亡率・神経学的後遺障害ともに未だ高く、克服するべき脳卒中の代表疾患の一つである。
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E3%81%8F%E3%82%82%E8%86%9C%E4%B8%8B%E5%87%BA%E8%A1%80
くも膜下出血の予後不良因子(脳血管攣縮)の予防と治療
どのような不良因子があるか
くも膜下出血の予後不良因子としては、主に3つあります。
・一時的損傷(直接的脳損傷)
・再出血
・脳血管攣縮
脳血管攣縮とは
薬剤や機械的刺激,血管作動性物質やホルモンの作用により,一過性に血管が異常収縮をおこし灌流組織の虚血を生じること。
https://www.jaam.jp/dictionary/dictionary/word/0502.html
わかりやすく言うと、血管が縮むことにより脳の血流が遮断・減少することで脳虚血が生じることです。
これは、発症2週間以内に生じる脳血流の低下で、遅発性脳虚血と呼ばれており、脳梗塞と同じ状態になります。
脳血管攣縮は、くも膜下出血後4-14日後に生じやすいとされており、くも膜下出血患者の30-70%に見られます。
くも膜下出血の程度が大きいほど血管攣縮が生じやすくなります。
脳血管攣縮に対する予防と治療
くも膜下出血では、脳血管攣縮の予防をいかに行うかがポイントになります(予後不良因子のため)。
基本的には、薬剤投与や脳血管内の循環量維持、血管内のボリューム維持が行われます。
血管攣縮は血腫の停滞によっても生じやすいため、ドレナージも行われます。
3H療法
3H療法は、
・循環血液量増加(Hypervolemia)
・人為的高血圧(Hypertension)
・血液希釈(Hemodilution)
からなります。
循環血液量増加では、代用血液の投与や輸血、アルブミン製剤などによって循環血液量を維持させます。
人為的高血圧では、脳血流維持のために高めに血圧を設定します。
血液希釈では、水分量増加により血液を希釈し血流をよくします。
脳槽・腰椎ドレナージ
血腫の排出を促して、脳圧の管理を行うものです。
血栓溶解療法
血栓溶解薬を髄腔内に投与します。
血腫を溶解することにより排出しやすくします。
全身的薬物投与
ファス汁塩酸塩水和物により平滑筋を弛緩させ、血管攣縮を予防します。
オザグレルナトリウムにより結晶板の凝集を予防し、血管拡張作用により血管攣縮を予防します。
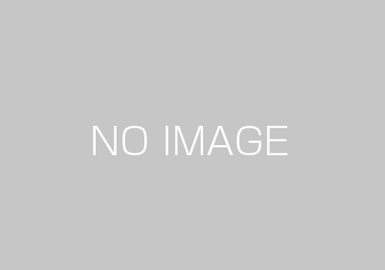
この記事へのコメントはありません。